宅地造成等規制法をわかりやすく解説
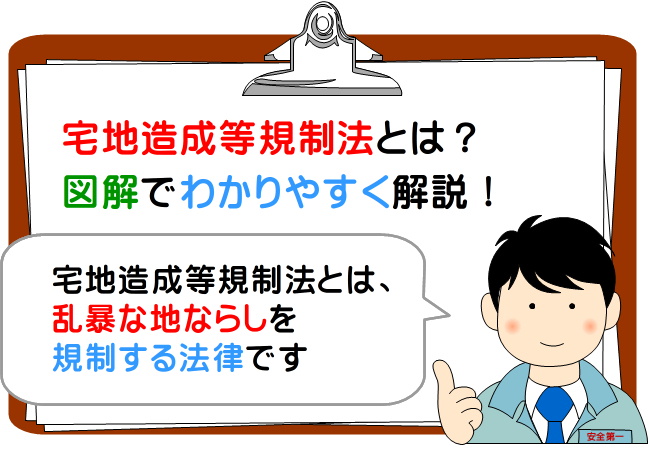
宅地造成等規制法とは、がけ崩れが心配される区域において、乱暴な地均し(じならし)を規制する法律です。
イラストと図を用いて宅造法をわかりやすく解説し、がけ崩れが心配される宅地造成規制区域が存在する都道府県などもご紹介しましょう。
目次
- 1. 宅地造成等規制法とは、乱暴な地ならしを規制する法律
- 1-1. あらためて宅地造成等規制法をわかりやすく解説
- 2. 宅地造成規制区域が存在する都道府県
- まとめ - 宅造法は三六災害により制定された
1. 宅地造成等規制法とは、乱暴な地ならしを規制する法律
それでは、宅地造成等規制法をわかりやすくご説明しましょう。
その前に、宅地造成等規制法という法律名の冒頭にある「宅地造成(たくちぞうせい)」の意味を理解してください。
宅地造成とは、建物を建てたり駐車場を設置するために行う、森林などを地均し(じならし)する行為です。
また、宅地造成は、既に建物が建てられている土地や、駐車場や資材置き場が設置されている土地を再び地ならしする行為でもあります。
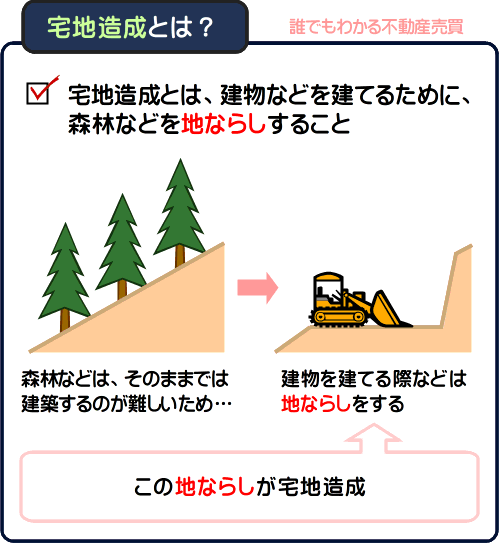
以上が、宅地造成等規制法の冒頭にある宅地造成の意味です。
つづいて、宅地造成等規制法をわかりやすく解説しましょう。
1-1. あらためて宅地造成等規制法をわかりやすく解説
宅地造成等規制法とは、崖崩れなどが心配される区域において、乱暴な宅地造成(地ならし)を規制する法律です。
崖崩れが心配される区域内で乱暴な宅地造成が行われれば、大雨の際に土砂災害が発生し、多くの人命が失われる虞があります。
そのため、宅地造成等規制法では、崖崩れや土砂災害が心配される区域を「宅地造成工事規制区域」と呼び、同区域内で一定の範囲を超える宅地造成を行う際は、都道府県知事などの許可が必要であると規定しています。
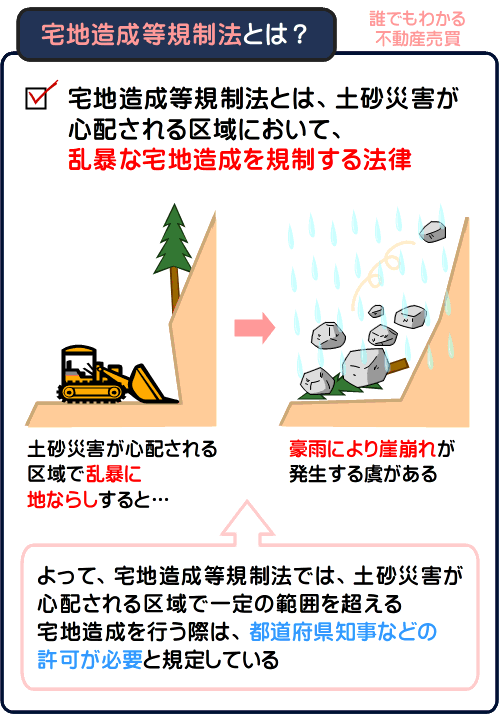
宅地造成等規制法で規定されている、都道府県知事などの許可を必要とする一定の範囲を超える宅地造成は以下のとおりです。
- 1. 切土(きりど:斜面を削る工事)により、高さが2mを超える崖(角度が30度を超える斜面)ができる宅地造成
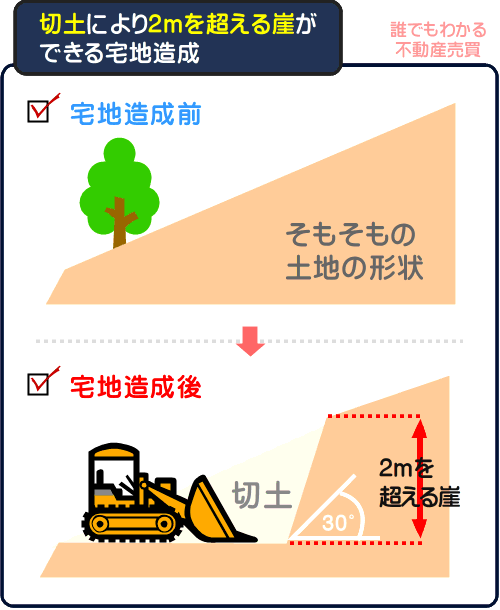
- 2. 盛土(もりど:土を盛る工事)により、高さが1mを超える崖(角度が30度を超える斜面)ができる宅地造成
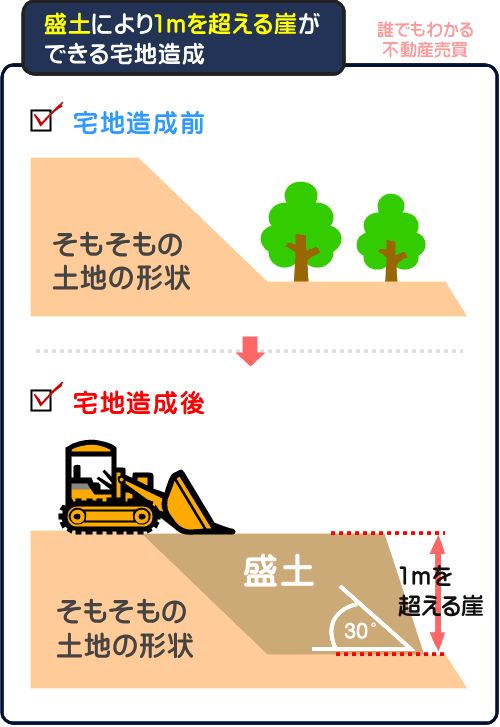
- 3. 切土と盛り土を同時に行うことにより、高さが2mを超える崖(角度が30度を超える斜面)ができる宅地造成
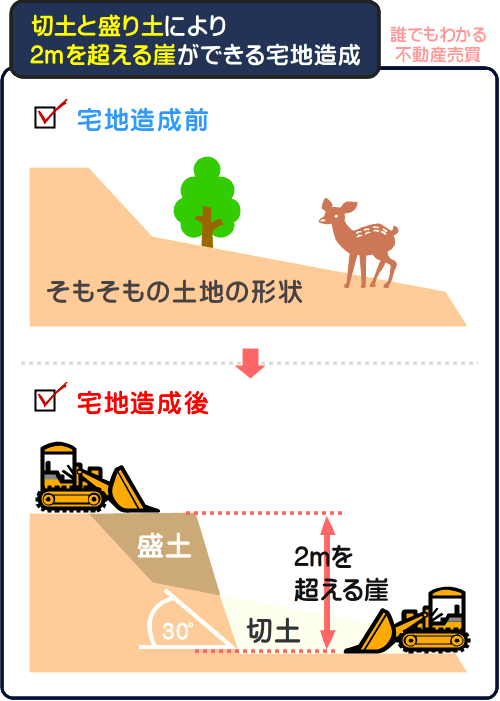
- 4. 切土や盛り土の有無にかかわらず、500㎡を超える宅地造成を行う場合
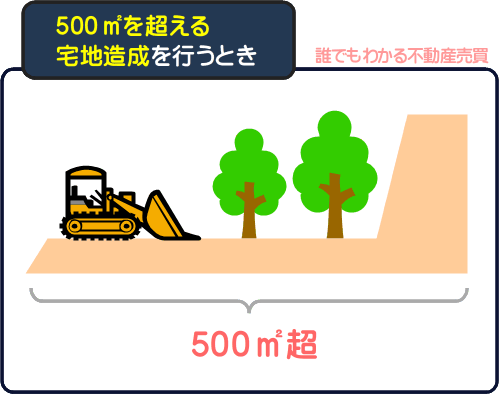
※ 都道府県知事などの許可を必要とする宅地造成の詳細は「国土交通省 宅地造成等規制法の概要」にて確認できる
宅地造成規制区域で以上の宅地造成を行う際は、自分で施行する場合であっても工事業者に依頼する場合であっても、都道府県知事などに申請しつつ許可を得なければなりません。
そして、宅地造成が完了すれば、都道府県知事などが現場を検査し、適切な工事が行われたと判断されれば検査済証が発行されます。
適切な工事が行われなかったと判断された場合は許可が取り消され、工事のやり直しを請求されます。
許可を得ず一定の範囲を超える宅地造成を行ったり、工事のやり直しに応じない場合は、一年以下の懲役や五十万円以下の罰金などが課せられます。
また、宅地造成等規制法では、宅地造成規制区域に既存する、がけ崩れなどが心配される建物が建っている土地や駐車場、資材置き場などの所有者に対して、都道府県知事などは改善命令を出すことができるとも規定しています。
以上が宅地造成等規制法の概要であり、わかりやすく解説すると、宅地造成等規制法とは土砂災害により、人命や資産などが失われることを防ぐための法律です。
2. 宅地造成規制区域が存在する都道府県
宅地造成等規制法とは、がけ崩れなどが心配される宅地造成規制区域で実施される宅地造成(地ならし)を規制する法律です。
宅地造成規制区域で一定の範囲を超える宅地造成を行う際は、都道府県知事などへの申請と許可、工事完了後の検査が必要となります。
そこで気になるのが、宅地造成規制区域の場所ですが、主に市街地、または今後市街化が予定される区域に指定されています。
以下に、平成31年4月1日の時点における宅地造成規制区域が存在する都道府県をご紹介しましょう。
宅地造成規制区域が存在する都道府県
| 都道府県名 | 宅地造成規制区域がある場所 |
|---|---|
| 北海道 | 札幌市、旭川市、函館市など |
| 岩手県 | 盛岡市、釜石市、宮古市 |
| 宮城県 | 仙台市 |
| 福島県 | 福島市 |
| 栃木県 | 宇都宮市、足利市、鹿沼市 |
| 群馬県 | 高崎市、桐生市 |
| 千葉県 | 千葉市、船橋市、銚子市など |
| 東京都 | 八王子市、町田市、世田谷区など |
| 神奈川県 | 横浜市、川崎市、横須賀市など |
| 石川県 | 金沢市 |
| 岐阜県 | 岐阜市、多治見市、土岐市 |
| 静岡県 | 浜松市、熱海市、伊東市など |
| 愛知県 | 名古屋市、岡崎市、豊田市など |
| 滋賀県 | 大津市、大津市、大津市 |
| 京都府 | 京都市、宇治市、城陽市など |
| 大阪府 | 堺市、高槻市、岸和田市など |
| 兵庫県 | 神戸市、姫路市、明石市など |
| 奈良県 | 奈良市、生駒市、王寺町など |
| 和歌山県 | 和歌山市、玉野市、笠岡市など |
| 岡山県 | 岡山市、倉敷市、玉野市など |
| 広島県 | 広島市、福山市、呉市など |
| 山口県 | 下関市、岩国市、周南市 |
| 愛媛県 | 松山市 |
| 高知県 | 高知市 |
| 福岡県 | 北九州市、福岡市 |
| 長崎県 | 長崎市、佐世保市 |
| 熊本県 | 熊本市、荒尾市 |
| 大分県 | 大分市、別府市 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
※ 詳細は国土交通省が公開する資料「宅地造成工事規制区域指定状況」にて確認できる
以上が平成31年4月1日の時点における、宅地造成規制区域が存在する主な都道府県と市町村です。
なお、表には北海道は札幌市、岩手県では盛岡市などに宅地造成規制区域があると記載しましたが、札幌市や盛岡市の全域が同区域に指定されているわけではありません。
たとえば、札幌市は北区、東区、白石区を除く丘陵地帯が宅地造成規制区域に指定されています。
また、盛岡市では、JR山岸駅やJR上米内駅の近くなど、一部の地域が指定されています。
詳細な宅地造成規制区域の位置は、各都道府県のホームページ内に設けられた検索窓に「宅地造成工事規制区域」などと入力しつつ検索することにより確認することが可能です。
ちなみに、誰でもわかる不動産売買では、宅地造成規制区域内に位置する不動産を購入する際の注意点などを解説するコンテンツも公開中です。
お時間のある方は、ぜひご覧ください。
関連コンテンツ
宅地造成工事規制区域とは?知っておくべき注意点など解説
まとめ - 宅造法は三六災害により制定された
宅地造成等規制法をわかりやすく解説しました。
宅地造成等規制法とは、がけ崩れなどの土砂災害が心配される宅地造成規制区域において、乱暴な宅地造成を規制する法律です。
宅地造成規制区域は、この記事の「2. 宅地造成規制区域が存在する都道府県」にてご紹介したとおり、北は北海道から南は鹿児島県まで、様々な都道府県に点在します。
宅地造成規制区域において、この記事の「1-1. あらためて宅地造成等規制法をわかりやすく解説」にてご紹介した一定の範囲を超える造成工事を行う際は、都道府県知事に申請しつつ許可を得なければなりません。
許可が下りれば宅地造成を行うことが可能ですが、工事完了後は検査が入ります。
検査に合格すれば都道府県知事などから検査済証が発行されますが、合格しない場合は許可自体が取り消しになり、工事のやり直しを求められるため留意してください。
また、宅地造成等規制法では、宅地造成規制区域に既存する、がけ崩れが心配される建物が建つ土地などの所有者に対して、都道府県知事などが改善命令を出すことができるとも規定しています。
なお、宅地造成等規制法は、昭和36年に発生した大雨による災害「昭和36年梅雨前線豪雨(通称:三六災害)」により、日本全国各地で1,500名を超える死傷者が出たことにより制定されました。
三六災害により被害を受けた長野県高森町の公民館では、当時の被害状況や復興の様子を収録した動画をYouTubeにて公開中です 宅地造成等規制法の制定経緯をお知りになりたい方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
ご紹介した内容が、宅地造成等規制法をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
記事公開日:2020年11月
こちらの記事もオススメです
