低炭素住宅とは?メリットなど解説
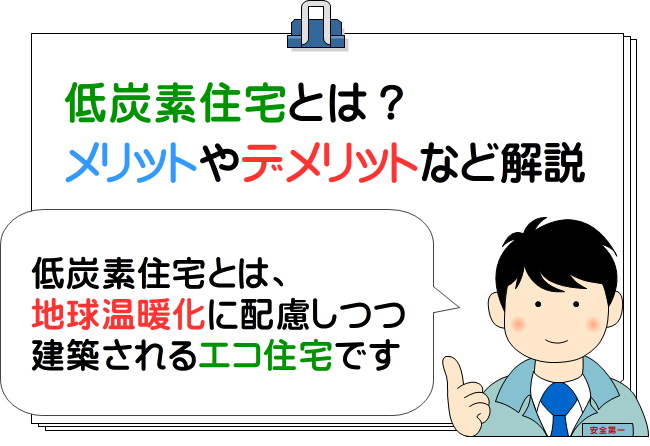
低炭素住宅とは、地球温暖化に配慮しつつ建築や改築された省エネ性能に優れたエコ住宅です。
低炭素住宅をわかりやすく解説し、低炭素住宅のメリットやデメリット、国土交通省が公開する低炭素住宅のわかりやすい資料などもご紹介しましょう。
目次
- 1. 低炭素住宅とは、光熱費などが安くなる省エネ住宅
- 2. 低炭素住宅のメリット
- 3. 低炭素住宅のデメリット
- まとめ - 国土交通省では、低炭素住宅のわかりやすい資料を公開中
1. 低炭素住宅とは、光熱費などが安くなる省エネ住宅
低炭素住宅とは、地球温暖化に配慮しつつ建築や改築されたエコ住宅であり、低炭素住宅という言葉に含まれる「炭素」は二酸化炭素の炭素です。
低炭素住宅は、各家庭から排出される二酸化炭素を削減することを目的として建築され、一般的な住宅より断熱性能が高いことが特徴となっています。
断熱性能が高ければ冷暖房の効きが良く、少ないエネルギー(電力)で快適に生活できます。
少ないエネルギーで快適に生活できれば電気の使用量が減り、それに伴い二酸化炭素の排出量を削減できます。
二酸化炭素の排出量が減れば地球温暖化を遅らせることが可能になり、電気の使用量が減れば光熱費が安くなり家計も助かります。
低炭素住宅は、地球にも家計にも優しい住宅というわけです。
また、低炭素住宅は、太陽光発電設備やエコキュート(低電力でお湯を沸かせる給湯器)などが設置されている場合もあります。
太陽光発電設備があれば自家発電しつつ化石燃料の消費を抑えることが可能であり、エコキュートがあれば少ない電力でお湯を沸かしつつ二酸化炭素の排出量を削減できます。
天井に180mm厚、外壁や床下に100mm厚の断熱材が入り、断熱性に優れた窓が使用され、朝日があたる南側の軒が広い、西日があたる西側の窓に日よけが付いているなどが低炭素住宅の特徴であり、低炭素住宅のイメージは以下のとおりです。
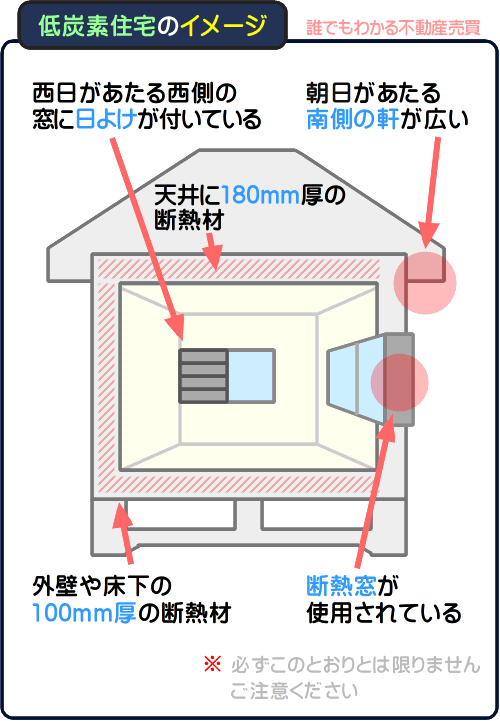
なお、断熱性に優れた全ての住宅が低炭素住宅ではないため注意してください。
低炭素住宅は「認定低炭素住宅」とも呼ばれ、市区町村などの所管行政庁から低炭素住宅であると認められた住宅のみが低炭素住宅です。
低炭素住宅を建築するためには、施主が低炭素住宅を建築するための計画を作成し、その計画書を所管行政庁に提出しつつ評価を受けなければなりません。
そして、その計画が低炭素住宅を建てる基準を満たすと所管行政庁が評価すれば、「低炭素建築物新築等計画の認定通知書」が発行されます。
低炭素建築物新築等計画の認定通知書が発行されつつ建築や改築された住宅が低炭素住宅です。
また、低炭素住宅の建築を希望する施主は、低炭素住宅を建築するための計画を作成し、その計画書を国土交通大臣が登録する専門機関に提出しつつ技術的審査を受けることもできます。
専門機関などが、その計画が低炭素住宅を建てる基準を満たすと評価すれば適合証が交付されます。
適合証の交付を受けた施主は、その適合証を添付した申請書を所管行政庁に提出することにより、低炭素建築物新築等計画の認定通知書がスムーズに発行されます。
低炭素住宅が建築される流れを図解でわかりやすくご説明すると以下のとおりです。
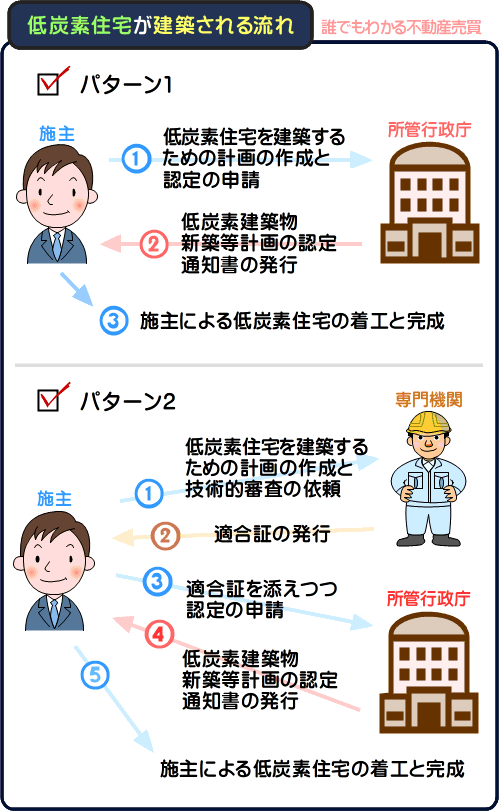
なお、「低炭素建築物新築等計画の認定通知書」を発行する所管行政庁は「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会|低炭素建築物新築等計画の認定を行う所管行政庁の検索」にて検索することが可能であり、適合証を発行する専門機関は同ページの検索結果に表示される「技術的審査(住宅)を実施可能な登録住宅性能評価機関はこちら」というリンクからご確認いただけます。
つづいて、低炭素住宅の詳細を質問と答えの形式でご紹介しましょう。
- 低炭素住宅とは?
- 低炭素住宅とは、地球温暖化に配慮しつつ建築や改築された省エネ性能に優れたエコな住宅です。
- 省エネ性能に優れた住宅は全て低炭素住宅ですか?
- いいえ。省エネ性能に優れていると市区町村などの所管行政庁から認定を受けた住宅のみが低炭素住宅です。
- 認定低炭素住宅とは?
- 認定低炭素住宅とは、所管行政庁から認定を受けた省エネ性能に優れた住宅です。
- 低炭素住宅と認定低炭素住宅の違いとは?
- 違いはありません。低炭素住宅とは市区町村などの所管行政庁から認定された省エネ性能に優れた住宅であり、それに該当する住宅を認定低炭素住宅と呼びます。
- 低炭素住宅のメリットとは?
- 低炭素住宅は省エネ性能に優れ、冷暖房が効きやすく光熱費を節約できるのがメリットです。
また、フラット35を利用しつつ低炭素住宅を取得すれば、返済開始当初から10年間にわたり金利が引き下げられる「フラット35S」が適用されます。
さらに、住宅ローンを利用しつつ低炭素住宅を取得すれば、住宅ローン控除の毎年の減税額の上限が40万円から50万円に引き上げられるというメリットもあります。 - 低炭素住宅のデメリットとは?
- 低炭素住宅は、断熱性に優れた高価な建材を用いて建築されます。
よって、建築費が高額であり、それに伴い不動産取得税や固定資産税なども高額になるのがデメリットです。 - 低炭素住宅に認定されるためにはどのような手続きが必要ですか?
- 低炭素住宅と認定される住宅を建築したり、既に建築されている住宅を低炭素住宅に改築するには、施主が低炭素住宅を建築、または改築する計画を作成し、その計画書を所管行政庁に提出しつつ認定申請を行う必要があります。
その計画が低炭素住宅を建築する基準を満たすと所管行政庁から評価されれば「低炭素建築物新築等計画の認定通知書」が発行され、その住宅は晴れて低炭素住宅に認定されます。
また、低炭素住宅を建築したり、既存の住宅を低炭素住宅に改築することを希望する施主は、計画を作成しつつ国土交通大臣が登録する専門機関に技術的審査を依頼することも可能です。
その計画が低炭素住宅を建築、または改築する基準を満たすと専門機関が評価すれば適合証が交付されます。
適合証を受け取った施主が、適合証を添付しつつ所管行政庁に認定申請を行えば、「低炭素建築物新築等計画の認定通知書」がスムーズに発行されます。
「低炭素建築物新築等計画の認定通知書」を発行する所管行政庁は「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会|低炭素建築物新築等計画の認定を行う所管行政庁の検索」にて検索することが可能であり、適合証を発行する専門機関は同ページの検索結果に表示される「技術的審査(住宅)を実施可能な登録住宅性能評価機関はこちら」というリンクからご確認いただけます。 - 低炭素住宅は、どのような場所に建築できますか?
- 低炭素住宅は、主に市街地のみに建築することが可能です。
低炭素住宅は地球温暖化に配慮しつつ建築される省エネ性能に優れた住宅ですが、二酸化炭素は主に市街地から排出され、市街地から排出される二酸化炭素を削減することが急務とされます。
よって、低炭素住宅は、二酸化炭素が多く排出される市街地のみに建築することが可能です。 - 低炭素建築物新築等計画の認定通知書とは?
- 低炭素建築物新築等計画の認定通知書とは、その住宅が低炭素住宅であることを証明する書面であり、低炭素住宅の建築や改築を希望する施主が、市区町村などの所管行政庁に認定申請を行うことにより発行されます。
低炭素建築物新築等計画の認定通知書を発行する所管行政庁は「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会|低炭素建築物新築等計画の認定を行う所管行政庁の検索」にて検索することが可能です。 - 認定低炭素住宅建築証明書とは?
- 認定低炭素住宅建築証明書とは、国土交通大臣が指定する指定確認検査機関や、国土交通大臣が登録した登録住宅性能評価機関、建築士事務所に所属する建築士などが交付する、その住宅が低炭素住宅に適合することを証明する書面です。
認定低炭素住宅建築証明書は、低炭素住宅を取得することにより適用される税制優遇措置を受ける際に税務署に提出する必要書類などとして活用できます。
認定低炭素住宅建築証明書を交付する指定確認検査機関は「国土交通省 建築基準法に基づく指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関について」にて、登録住宅性能評価機関は「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会|登録住宅性能評価機関の検索」にて確認することが可能です。
2. 低炭素住宅のメリット
低炭素住宅とは、地球温暖化に配慮して建築された省エネ住宅です。
そして、低炭素住宅を取得すれば、フラット35の金利が引き下げられる、住宅ローン控除でより多くの所得税が減税されるなどのメリットがあります。
ここから、低炭素住宅のメリットをご紹介しましょう。
フラット35の金利が引き下げられる
フラット35とは、銀行と住宅金融支援機構が協力して貸し出す国民的な住宅ローンです。
低炭素住宅を購入するためにフラット35を利用すれば、返済開始から10年間にわたり金利が引き下げられる「フラット35S」が適用されます。
筆者がこの記事を作成する2021年2月現在、フラット35の金利は1.32%などですが、フラット35Sが適用されれば返済開始から10年間にわたり金利が0.25%引き下げられ1.07%などになります。
このようにフラット35Sが利用できることが、低炭素住宅を取得するメリットのひとつです。
ちなみに、金利1.32%で5,000万円を借り入れ、元利均等返済、ボーナス払いなしで35年間で返済する場合における総返済額は6,247万円です。
これに対して、同じ条件で5,000万円を借り入れ、返済開始から10年間にわたり金利が1.07%であれば、総返済額は6,127万円となります。
低炭素住宅の購入を検討しつつフラット35の適用を希望される方がいらっしゃいましたら、是非ご参考になさってください。
住宅ローン控除の減税額の上限が毎年50万円になる
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用しつつ住宅を購入することにより適用される減税制度です。
住宅ローン控除が適用されれば、住宅を購入後10年間にわたり、毎年40万円を上限とするその年の年末の住宅ローン残高の1%が所得税から減税されます。
一方、低炭素住宅を取得しつつ住宅ローン控除の適用を受ければ、住宅を購入後10年間にわたり、毎年50万円を上限とするその年の年末の住宅ローン残高の1%が所得税から減税されます。
このように、住宅ローン控除の毎年の減税額の上限が40万円から50万円に引き上げられることが、低炭素住宅のメリットのひとつです。
なお、住宅ローン控除は、支払う所得税から40万円などが減税される制度であり、40万円などが支給される制度ではないため注意してください。
住宅ローン控除は支払う所得税から最高40万円などが減税される制度であり、支払う所得税額以上は減税されません。
また、筆者がこの記事を作成する令和3年2月現在、住宅ローン控除の適用を受けるためには、令和3年12月31日までに住宅を購入する必要があります。
低炭素住宅を取得することにより住宅ローン控除の上限が引き上げられることの詳細は、「国税庁タックスアンサーNo.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」の「4 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」にてご確認いただけます。
登録免許税の税率の引き下げ
住宅や土地などの不動産を取得すると登記が必要です。
登記とは、法務省の地方支部局である法務局に設置されている登記簿と呼ばれる公の帳簿に、その不動産の所有者などに関する情報を記す行為です。
不動産を取得した方は、自身がその不動産の所有者になったことを登記することにより所有権を主張できるようになります。
登録免許税とは、その登記の際に課せられる税金です。
そして、低炭素住宅を取得すれば、その登記の際に課せられる税金である登録免許税の税率が引き下げられ、税額が安くなります。
登録免許税が安くなることが、低炭素住宅を取得することにより得るメリットのひとつです。
ただし、筆者がこの記事を作成する令和3年2月現在、登録免許税の税率が引き下げられるのは、令和4年3月31日までに低炭素住宅を取得しつつ登記した場合に限られるため注意してください。
また、登録免許税の引き下げは、所有権保存登記の税率が0.15%から0.1%に、所有権移転登記の税率が0.3%から0.1%となっています。
低炭素住宅を取得することにより登録免許税の税率が引き下げられることの詳細は、「国税庁タックスアンサーNo.7191 登録免許税の税額表」の「(3)住宅用家屋の軽減税率」にてご確認いただけます。
住宅取得資金贈与の非課税の上限引き上げ
親から子へ住宅を購入するための資金が贈与されれば、贈与された額に応じて贈与税が課せられます。
しかし、祖父母や父母から子や孫へ向けて、一定の条件を満たしつつ住宅を購入するための資金が贈与されれば、一定の額までの贈与に課せられる贈与税が非課税になる特例があります。
この特例を「住宅取得資金贈与の非課税」などと呼びます。
たとえば、令和3年4月1日から令和3年12月31日までに一般的な住宅を購入するための資金が贈与され、住宅取得資金贈与の非課税が適用されれば、700万円までの贈与に贈与税が掛かりません。
このように住宅の購入資金が贈与された場合に適用される「住宅取得資金贈与の非課税」ですが、低炭素住宅を購入するための資金が贈与されれば、非課税の上限に500万円が加算されます。
例を挙げると、令和3年4月1日から令和3年12月31日までに低炭素住宅を購入するための資金が贈与され、「住宅取得資金贈与の非課税」が適用されれば、1,200万円までの贈与に贈与税が掛からないという具体です。
「住宅取得資金贈与の非課税」が適用された場合における非課税の上限に500万円が上乗せされることが、低炭素住宅のメリットのひとつです。
低炭素住宅の購入資金が贈与された場合に「住宅取得資金贈与の非課税」の上限が引き上げられることの詳細は、「国税庁タックスアンサーNo.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の「2 非課税限度額」にてご確認いただけます。
容積率の緩和
容積率とは、その土地に建築できる建物の床面積を意味し、%で表します。
たとえば、容積率が100%の165㎡(約50坪)の土地の場合は「165㎡×100%=165㎡」と計算し、その土地には床面積が165㎡までの建物を建築することが可能です。
このように容積率とは、その土地に建築できる建物の床面積を表しますが、蓄電池や蓄熱槽などの省エネ設備を設置しつつ低炭素住宅を建築した場合は、それらを設置した床部分の面積が容積率に含まれません。
例を挙げると、容積率が100%の165㎡の土地には床面積が165㎡までの建物を建築できますが、蓄電池や蓄熱槽を設置した部屋の床面積が20㎡の場合は、185㎡までの建物を建築できるといった具体です。
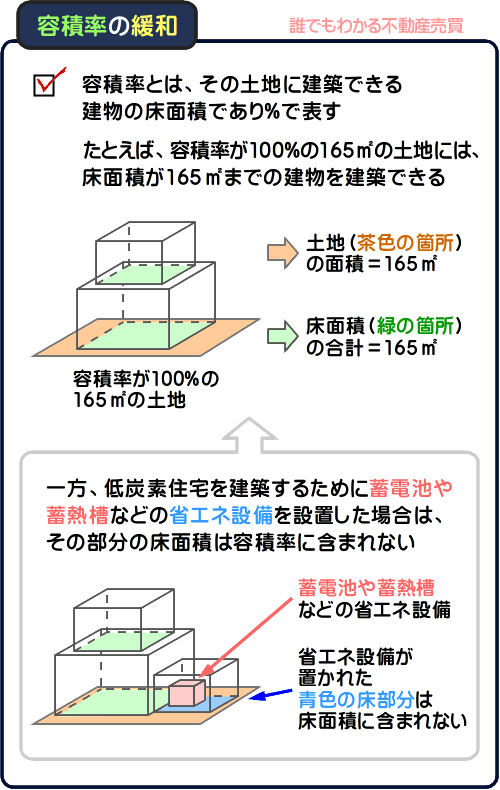
蓄電池や蓄熱槽などの省エネ設備を設置した部分の床面積が容積率に含まれず、より広い住宅を建築できることが低炭素住宅のメリットのひとつです。
ただし、容積率が緩和される上限は、20分の1までとなっているためご注意ください。
3. 低炭素住宅のデメリット
低炭素住宅には、光熱費を節約できる、フラット35の金利が引き下げられるなどのメリットがありますが、建築費が高いなどのデメリットもあります。
ここから、低炭素住宅のデメリットをご紹介しましょう。
建築費が高い
低炭素住宅とは省エネ性能に優れた住宅であり、通常の住宅より高い断熱性を有する建材で建築されます。
それにより冷暖房の効きが良く光熱費を節約できるなどのメリットがありますが、高い断熱性を有する建材は高価であり、それに伴い建築費が高額になります。
どの程度高額になるかは、低炭素住宅の仕様によって異なるため断言できませんが、おそらくはフラット35の金利引き下げ分や住宅ローン控除の減税額の上限引き上げ分より大幅に高くなります。
固定資産税が高い
低炭素住宅とは省エネ性能に優れたエコ住宅であり、高い断熱性を有する建材で建築されます。
高い断熱性を有する建材は高価であり、高価な建材が使用された住宅は固定資産税も高くなるのが通例です。
どの程度高くなるかは、低炭素住宅の床面積などによって異なるため断言できませんが、通常の住宅の1.2~1.3倍程度などになることも珍しくありません。
まとめ - 国土交通省では、低炭素住宅のわかりやすい資料を公開中
低炭素住宅をわかりやすく簡単にご説明しました。
低炭素住宅とは、地球温暖化に配慮して建築や改築された省エネ住宅であり、光熱費を節約できる、フラット35の金利が引き下げられる、住宅ローン控除の毎年の減税額の上限が引き上げられるなどのメリットがあります。
一方、低炭素住宅には、建築費や不動産取得税、固定資産税が高いなどのデメリットがあるため留意してください。
なお、国土交通省では、低炭素住宅をわかりやすく解説する以下の資料を公開中です。
国土交通省が公開する低炭素住宅の資料
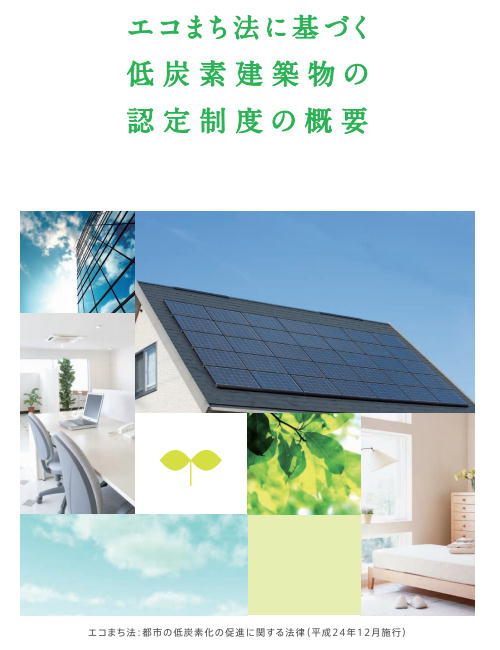
同資料では、低炭素建築物の認定制度の概要が解説されていますが、低炭素建築物とは低炭素住宅を含む建築物を意味します。
低炭素住宅をさらに深く理解したいと希望される方がいらっしゃいましたら、ぜひ同資料をご覧ください。
ご紹介した内容が、低炭素住宅をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
記事公開日:2021年2月
こちらの記事もオススメです
