イラスト付きでわかりやすい!リフォーム減税を図解で解説
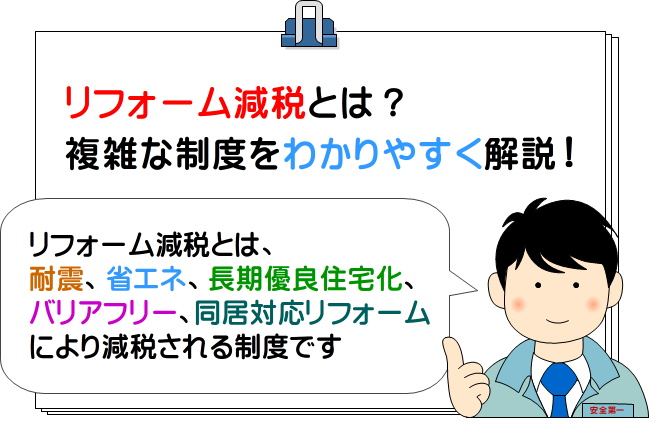
リフォーム減税とは、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、同居対応リフォーム、長期優良住宅化リフォームを実施することにより、所得税や固定資産税が減税される制度です。
制度の内容をわかりやすく解説し、エコキュートの導入や外壁塗装にリフォーム減税が適用されるかなどご紹介しましょう。
なお、リフォーム減税は制度の内容が複雑なため、この記事ではあらましをご説明します。
実際にリフォーム減税の適用を目的としてリフォームを実施する際は、必ず最寄りの税務署や市区町村役場にて詳細をご確認ください。
目次
- 1. リフォーム減税とは、所得税や固定資産税が減税される制度
- 1-1. 耐震リフォーム
- 1-2. バリアフリーリフォーム
- 1-3. 省エネリフォーム
- 1-4. 同居対応リフォーム
- 1-5. 長期優良住宅化リフォーム
- 2. リフォーム減税でエコキュートは対象?
- 3. 外壁塗装はリフォーム減税の対象?
- まとめ - リフォーム減税の適用には確定申告や届出が必要
1. リフォーム減税とは、所得税や固定資産税が減税される制度
冒頭でご紹介したとおり、リフォーム減税とは、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、同居対応リフォーム、長期優良住宅化リフォームを実施することにより所得税や固定資産税が減税される制度です。
そして、リフォーム減税は、リフォーム費用の決済方法により投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税の3つに細分化されます。
投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税の詳細は以下のとおりです。
投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税の詳細
- 投資型減税
- 現金一括払い、または返済期間が5年未満などのローンを利用しつつリフォーム代金を決済した場合は、リフォーム減税における投資型減税の適用を希望することが可能です。
投資型減税が適用されれば、リフォームが完了した年の収入に課せられる所得税から最高25万円などが減税されます。 - ローン型減税
- 返済期間が5年以上のローンを利用しつつリフォーム代金を決済した場合は、リフォーム減税におけるローン型減税の適用を希望することが可能です。
ローン型減税が適用されれば、5年間にわたり所得税から毎年最高12万5,000円が減税されます。 - 住宅ローン減税
- 返済期間が10年以上のローンを利用しつつリフォーム代金を決済した場合は、住宅ローン減税の適用を希望することが可能です。
住宅ローン減税が適用されれば、10年間などにわたり所得税から毎年最高40万円が減税されます。
上記のように、リフォーム減税は代金の決済方法により投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税の3つに分岐します。
ただし、耐震リフォームに限りローン型減税の適用は希望できないため注意してください。
図解でわかりやすくご説明すると以下のとおりです。
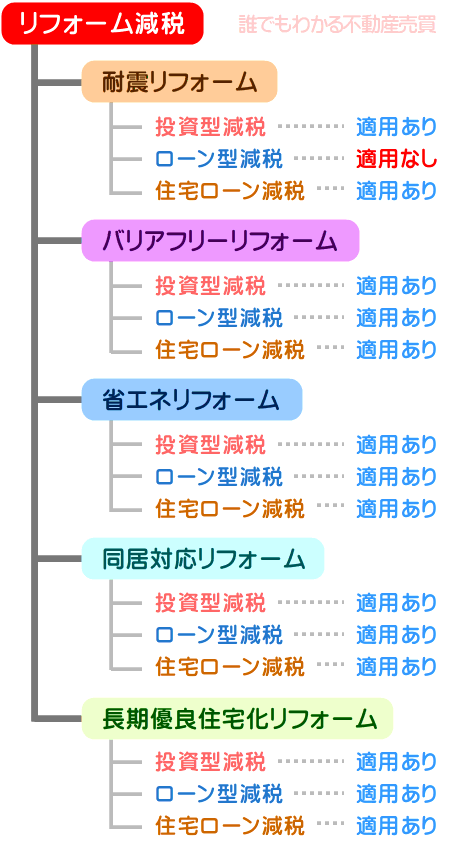
ここから、リフォーム減税が適用される耐震リフォーム、省エネリフォーム、同居対応リフォーム、長期優良住宅化リフォームの詳細をわかりやすくご説明しましょう。
1-1. 耐震リフォーム
耐震リフォームには、投資型減税と住宅ローン減税が適用されます。
主な適用条件や減税額は以下のとおりです。
- 投資型減税
- 現金一括払い、または返済期間が10年未満のリフォーム用のローンを利用しつつ昭和56年5月31日以前に建築された住宅などに耐震リフォームを実施すれば、投資型減税の適用を希望することが可能です。
投資型減税が適用されれば、リフォームを実施した年の収入に課せられる所得税から最大25万円が減税されます。 - 住宅ローン減税
- 返済期間が10年以上のリフォーム用のローンを利用しつつ資金を借り入れ、費用が100万円を超える耐震リフォームなどを実施すれば住宅ローン減税の適用を希望することが可能です。
住宅ローン減税が適用されれば、10年間などにわたり、毎年40万円を上限とする年末のローン残高の1%が所得税から減税されます。
年末のローン残高の1%とは、その年の年末に残る返済額の1%であり、300万円を借り入れしつつ毎年30万円ずつ返済する場合は以下のように推移します。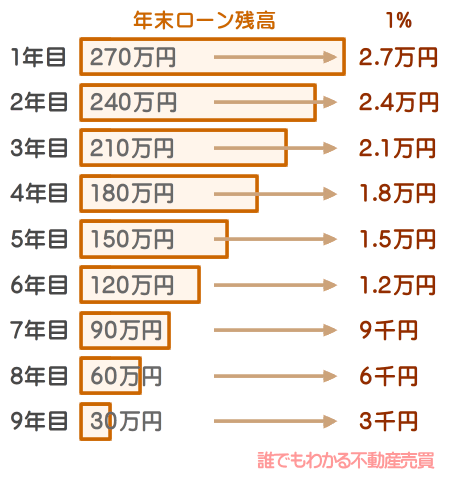
以上が耐震リフォームにおける投資型減税、住宅ローン減税の詳細です。
なお、昭和57年1月1日以前から所在する住宅に、費用の総額が50万円を超える耐震リフォームなどを実施した場合は、固定資産税の減税制度の適用も希望することが可能です。
固定資産税の減税制度が適用されれば、耐震リフォームを実施した翌年の固定資産税が2分の1に減税されます。
ちなみに、誰でもわかる不動産売買では、リフォーム減税における耐震リフォームの制度の詳細をわかりやすく解説するコンテンツも公開中です。
お時間のある方は、ぜひご覧ください。
関連コンテンツ
耐震リフォームで減税される条件とは?簡単・簡潔に解説
1-2. バリアフリーリフォーム
バリアフリーリフォームには、投資型減税とローン型減税、住宅ローン減税が適用されます。
それぞれの主な適用条件や減税額は以下のとおりです。
- 投資型減税
- 現金一括払い、または返済期間が5年未満のローンを利用し、50万円を超えるバリアフリーリフォームなどを実施すれば投資型減税の適用を希望することが可能です。
バリアフリーリフォームにおける投資型減税が適用されれば、リフォームを実施した年の収入に課せられる所得税から最高20万円が減税されます。 - ローン型減税
- 返済期間が5年以上のローンを利用し、50万円を超えるバリアフリーリフォームなどを実施すればローン型減税の適用を希望することが可能です。
ローン型減税が適用されれば、5年間にわたり、毎年12万5,000円を上限とする年末のローン残高の1%が所得税から減税されます。 - 住宅ローン減税
- 返済期間が10年以上のリフォーム用のローンを利用し、工事費が100万円を超えるバリアフリーリフォームなどを実施すれば、住宅ローン減税の適用を希望することが可能です。
住宅ローン減税が適用されれば、10年間などにわたり、毎年40万円を上限とする年末のローン残高の1%が所得税から減税されます。
以上がバリアフリーリフォームにおける投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税の詳細です。
なお、費用の総額が50万円を超えるバリアフリーリフォームを実施すれば、固定資産税の減税制度の適用も希望できます。
固定資産税の減税制度が適用されれば、バリアフリーリフォームを実施した翌年の固定資産税を3分の2に減税することが可能です。
バリアフリーリフォームを対象とするリフォーム減税の詳細は、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が公開する資料「2. バリアフリーリフォーム編」にてご確認いただけます。
1-3. 省エネリフォーム
省エネリフォームには、投資型減税とローン型減税、住宅ローン減税が適用されます。
それぞれの主な適用条件や減税額は以下のとおりです。
- 投資型減税
- 現金一括払い、または返済期間が5年未満のローンを利用し、50万円を超える費用を掛けつつ全ての居室の全ての窓を断熱窓に交換するなどの省エネリフォームを実施すれば、投資型減税の適用を希望することが可能です。
省エネリフォームにおける投資型減税が適用されれば、リフォームを実施した年の収入に課せられる所得税から最高25万円(断熱窓に交換すると共に太陽光パネルも設置した場合は最大35万円)が減税されます。 - ローン型減税
- 返済期間が5年以上のローンを利用し、50万円を超える省エネリフォームなどを実施すれば、ローン型減税の適用を希望することが可能です。
ローン型減税が適用されれば、5年間にわたり、毎年12万5,000円を上限とする年末のローン残高の1%が所得税から減税されます。 - 住宅ローン減税
- 返済期間が10年以上のリフォーム用のローンで資金を借り入れ、工事費が100万円を超える省エネリフォームなどを実施すれば、住宅ローン減税の適用を希望することが可能です。
住宅ローン減税が適用されれば、10年間などにわたり、毎年40万円を上限とする年末のローン残高の1%が所得税から減税されます。
ただし、住宅ローン減税を適用させるためには、リフォーム完了後の床面積が50㎡を超える省エネリフォームを実施する必要があるため注意してください。
以上が省エネリフォームにおける投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税の詳細です。
なお、費用の総額が50万円を超える省エネリフォームなどを実施した場合は、固定資産税の減税制度の適用も希望することが可能です。
固定資産税の減税制度が適用されれば、省エネリフォームを実施した翌年の固定資産税が3分の2に減税されます。
ちなみに、誰でもわかる不動産売買では、リフォーム減税が適用される省エネリフォームの条件などをわかりやすく解説するコンテンツも公開中です。
省エネリフォームを検討しつつリフォーム減税の適用を希望される方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
関連コンテンツ
省エネリフォームで減税される条件とは?簡単・簡潔に解説
1-4. 同居対応リフォーム
同居対応リフォームとは、親、子、孫などの多世代が一戸の住宅に居住するために実施する、キッチンや浴室、トイレ、玄関などを増設する工事です。
同居対応リフォームには、投資型減税とローン型減税、住宅ローン減税が適用され、それぞれの主な適用条件や減税額は以下のとおりとなっています。
- 投資型減税
- 現金一括払い、または返済期間が5年未満のローンを利用し、50万円を超える費用を掛けつつ同居対応リフォームを実施すれば、投資型減税の適用を希望することが可能です。
投資型減税が適用されれば、リフォームを実施した年の収入に課せられる所得税から最大25万円が減税されます。 - ローン型減税
- 返済期間が5年以上のローンを利用し、50万円を超える同居対応リフォームなどを実施すれば、ローン型減税の適用を希望することが可能です。
ローン型減税が適用されれば、5年間にわたり、毎年12万5,000円を上限とする年末のローン残高の1%が所得税から減税されます。
ただし、ローン型減税を適用させるためには、自らが所有しつつ居住する住宅に、リフォーム完了後の床面積が50㎡以上になる同居対応リフォームを実施する必要があるため注意してください。 - 住宅ローン減税
- 返済期間が10年以上のローンを利用し、工事費が100万円を超える増築などを伴う大規模な同居対応リフォームなどを実施すれば、住宅ローン減税の適用を希望することが可能です。
住宅ローン減税が適用されれば、10年間などにわたり、毎年40万円を上限とする年末のローン残高の1%が所得税から減税されます。
以上が同居対応リフォームにおける投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税の詳細です。
同居対応リフォームを対象とするリフォーム減税の詳細は、住宅リフォーム推進協議会が公開する資料「4.同居対応リフォーム編」にてご確認いただけます。
1-5. 長期優良住宅化リフォーム
長期優良住宅化リフォームとは、住宅の換気性や通気性、防腐性、防湿性などを高める工事であり、実施することにより住宅の耐久性を向上させることが可能です。
そして、長期優良住宅化リフォームには、投資型減税とローン型減税、住宅ローン減税が適用され、それぞれの主な適用条件や減税額は以下のとおりとなっています。
- 投資型減税
- 現金一括払い、または返済期間が5年未満のローンを利用し、50万円以上の費用を掛けつつ長期優良住宅化リフォームと耐震リフォーム、または長期優良住宅化リフォームと省エネリフォームを実施すれば、投資型減税の適用を希望することが可能です。
投資型減税が適用されれば、リフォームを実施した年の収入に課せられる所得税から最高25万円(長期優良住宅化リフォーム、耐震リフォーム、省エネリフォームの3つの工事を同時に実施した場合は最高50万円)が減税されます。 - ローン型減税
- 返済期間が5年以上のローンを利用し、50万円を超える長期優良住宅化リフォームと省エネリフォームを同時に実施すれば、ローン型減税の適用を希望することが可能です。
ローン型減税が適用されれば、5年間にわたり、毎年12万5,000円を上限とする年末のローン残高の1%が所得税から減税されます。 - 住宅ローン減税
- 返済期間が10年以上のローンを利用しつつ100万円を超える大規模な長期優良住宅化リフォームなどを実施すれば、住宅ローン減税の適用を希望することが可能です。
住宅ローン減税が適用されれば、10年間などにわたり、毎年40万円を上限とする年末のローン残高の1%が所得税から減税されます。
以上が長期優良住宅化リフォームにおける投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税の詳細です。
長期優良住宅化リフォームにおける投資型減税とローン型減税は、長期優良住宅化リフォームだけでは適用されず、耐震リフォームや省エネリフォームと共に実施することにより適用されるため注意してください。
なお、50万円を超える費用を掛けつつ、長期優良住宅化リフォームと耐震リフォーム、または省エネリフォームを実施した場合などは、固定資産税の減税制度の適用も希望することが可能です。
固定資産税の減税制度が適用されれば、リフォームを実施した翌年の固定資産税が3分の1に減税されます。
長期優良住宅化リフォームを対象とするリフォーム減税の詳細は、住宅リフォーム推進協議会が公開する資料「5.長期優良住宅化リフォーム編」にてご確認いただけます。
2. リフォーム減税でエコキュートは対象?
オール電化のご家庭には欠かせないエコキュートですが、エコキュートだけを単体で導入する場合は、残念ながらリフォーム減税は適用されません。
ただし、50万円を超える費用をかけつつ、住宅の全ての居室の全ての窓に断熱工事を実施すると共にエコキュートを導入した場合は、省エネリフォームを対象とするリフォーム減税が適用されます。
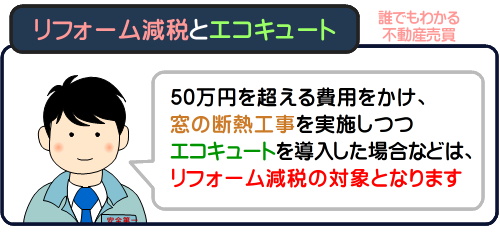
その根拠は、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が公開するリフォーム減税に関する資料「3.省エネリフォーム編」の76ページ、及び83ページにてご確認いただけます。
気になる減税額はリフォーム代金を支払う方法によって異なり、以下のとおりです。
エコキュートの導入によるリフォーム減税の減税額
| 代金の支払方法 | 減税額 |
|---|---|
| 現金一括払い、または返済期間が5年未満のローンを利用し、費用の総額が50万円を超えるエコキュートを導入するリフォームを実施した場合 | リフォームを実施した翌年の所得税から最大25万円などが減税 |
| 返済期間が5年以上のローンを利用し、費用の総額が50万円を超えるエコキュートを導入するリフォームを実施した場合 | 5年間にわたり、毎年12万5,000円を上限とする年末のローン残高の1%が所得税から減税 |
| 返済期間が10年以上のローンを利用しつつ、費用の総額が100万円を超えるエコキュートを導入するリフォームを実施した場合 | 10年間などにわたり、毎年40万円を上限とする年末のローン残高の1%が所得税から減税 |
エコキュートも対象となる省エネリフォームに関するリフォーム減税の詳細は、この記事の「1-3. 省エネリフォーム」にてご確認いただけます。
3. 外壁塗装はリフォーム減税の対象?
住宅は10年に1度など外壁を塗り替える大規模な修繕が必要ですが、一定の条件を満たす外壁塗装を実施すれば、リフォームを対象とする住宅ローン減税が適用されます。
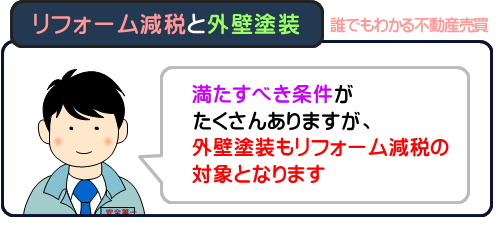
ただし、満たすべき条件のハードルが高く、主な条件は以下のとおりです。
外壁塗装が住宅ローン減税の対象となる主な条件
- 100万円を超える費用を掛けつつ外壁塗装などの大規模な修繕を実施する
- 返済期間が10年以上のリフォーム用のローンを利用しつつ資金を借り入れ、代金を決済する
- 床面積が50㎡以上の住宅に外壁塗装を行う
- 自らが所有しつつ居住する住宅に外壁塗装を行う
以上の条件などを満たす外壁塗装を行えば、リフォームを対象とする住宅ローン減税が適用されます。
住宅ローン減税が適用されれば、10年間などにわたり、毎年40万円を上限とするローンの返済残高の1%が所得税から減税されます。
リフォームを対象とする住宅ローン減税の適用条件や減税額の詳細は、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が公開する資料「6.住宅ローン減税編」にてご確認いただけます。
まとめ - リフォーム減税の適用には確定申告や届出が必要
リフォーム減税をわかりやすく解説し、エコキュートの導入や外壁塗装にリフォーム減税が適用されるかなどご紹介しました。
リフォーム減税とは、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、同居対応リフォーム、長期優良住宅化リフォームを対象とする減税制度です。
リフォーム減税は、リフォーム代金の決済方法により投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税、固定資産税の減税などに細分化され、適用されれば所得税や固定資産税が減税されます。
エコキュートだけを導入する場合はリフォーム減税の対象外ですが、50万円を超える費用を掛けつつエコキュートを導入すると共に断熱工事を実施した場合は、リフォーム減税の対象となります。
そして、100万円を超える外壁塗装を行い、返済期間が10年以上のローンを利用しつつ代金を決済する場合などは、住宅ローン減税が適用されます。
リフォーム減税をお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。
なお、所得税が減税されるリフォーム減税を適用させるためには、一定の要件を満たすリフォームを実施した上で、必要書類を添付しつつ税務署に確定申告を行う必要があります。
確定申告書に添付すべき必要書類は、実施したリフォームによって異なり、以下の国税庁のページにて確認することが可能です。
リフォーム減税の必要書類が記された国税庁のページへのリンク
| リフォームの種類 | 国税庁のページ |
|---|---|
| 耐震リフォーム | 国税庁タックスアンサーNo.1222 耐震改修工事をした場合 |
| バリアフリーリフォーム | 国税庁タックスアンサーNo.1220 バリアフリー改修工事をした場合、または国税庁タックスアンサーNo.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合 |
| 省エネリフォーム | 国税庁タックスアンサーNo.1219 省エネ改修工事をした場合、または国税庁タックスアンサーNo.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合 |
| 同居対応リフォーム | 国税庁タックスアンサーNo.1224 多世帯同居改修工事をした場合、または国税庁タックスアンサーNo.1223 借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合 |
| 長期優良住宅化リフォーム | 国税庁タックスアンサーNo.1227 耐久性向上改修工事をした場合 |
| 住宅ローン減税 | 国税庁タックスアンサーNo.1216 増改築等をした場合 |
また、固定資産税が減税されるリフォームを実施した場合は、リフォーム完了後3ヵ月以内に、市区町村役場に必要書類を添付した申請書を提出する必要があります。
申請書に添付すべき必要書類は、市区町村役場のホームページ内に設置された検索窓に「リフォーム 減税 固定資産税」などと入力しつつ検索することにより確認することが可能です。
ご紹介した内容が、リフォーム減税をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
記事公開日:2020年11月
こちらの記事もオススメです
