固定資産税はいくらくらい?一戸建ての税額の目安を解説
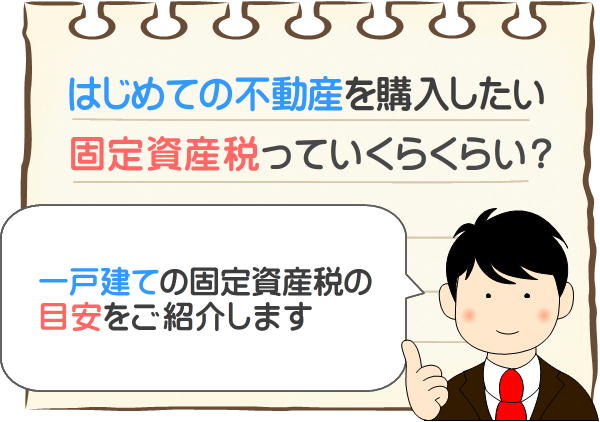
不動産の固定資産税は、高ければ25万円以上など、安ければ2万円から3万円程度など様々です。
はじめて不動産を購入する方へ向けて、新築の一戸建てと、一戸建て中古住宅の固定資産税がいくらくらいかご紹介しましょう。
目次
1. 新築の一戸建ての固定資産税はいくらくらい?
新築の一戸建てを購入すると、一部例外を除き、その家屋と家屋が建つ土地を所有することとなります。
そして、家屋と土地に個別に固定資産税が課せられます。
家屋と土地の固定資産税を合計すると、高ければ25万円以上など、安ければ12万円から13万円程度などですが、建築費や立地条件などによって税額が大きく変わります。
以下に、新築の家屋と土地の固定資産税がいくらくらいか簡単にご紹介しましょう。
1-1. 新築の一戸建て家屋の固定資産税はいくらくらい?
新築の家屋の固定資産税は、高ければ20万円以上など、安ければ10万円程度などです。
20万円以上から10万円程度というと開きがありますが、その理由は家屋の固定資産税が計算される方法にあります。
新築の家屋は、再建築費を基に計算されます。
再建築費とは、その家屋と同一の家屋を現時点で新築する際に必要となる材料費と労務費などの合計です。
たとえば、その家屋と同一の家屋を現時点で新築するために、500万円の材料費と500万円の労務費が必要となる家屋があるとしましょう。
その家屋の再建築費は1,000万円などとなり、その家屋の新築時の固定資産税は1,000万円の1.4%である14万円などとなります。
また、材料費が1,000万円、労務費が1,000万円である再建築費が2,000万円の家屋があったとしましょう。
その家屋の新築時の固定資産税は、2,000万円の1.4%である28万円などとなります。
このように新築の一戸建ての家屋の固定資産税は、再建築費を基に計算されます。
再建築費は家屋によって異なるため、再建築費を基に計算される固定資産税も一定ではありません。
よって、新築の家屋の固定資産税がいくらくらいか断言できず、高ければ20万円以上など、安ければ10万円程度などになるというわけです。
とはいうものの、税額に傾向がないわけではありません。
再建築費と販売価格は比例し、再建築費が高額な家屋は販売価格も高くなるため、販売価格が高い家屋は固定資産税も高くなる傾向があります。
反対に、再建築費が安価な家屋は販売価格も安くなるため、販売価格が安い家屋は固定資産税も安くなる傾向があります。
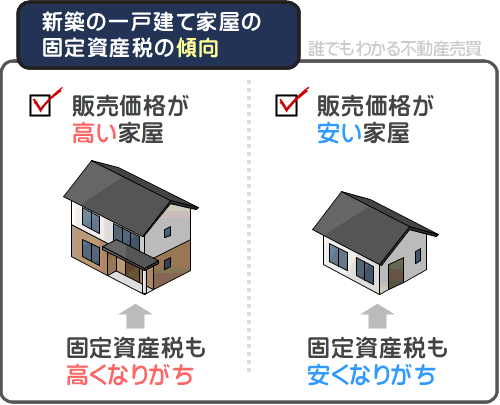
なお、一定の条件を満たせば、新築の家屋に掛かる固定資産税は3年間などにわたり2分の1に減額されます。
満たすべき主な条件は、以下のとおりです。
新築の一戸建て家屋の固定資産税が3年間などにわたり減額される条件
- 令和4年3月31日までに新築された家屋を取得した
- 床面積が50㎡以上280㎡以下の家屋を取得した
1-2. 新築の一戸建ての土地部分の固定資産税はいくらくらい?
新築の家屋が建つ土地の固定資産税は、高ければ5万円から6万円程度など、安ければ2万円から3万円程度などです。
家屋が建つ土地の固定資産税は、最寄りの標準地の公示地価、または基準地の基準地価を参考に計算されます。
公示地価とは、毎年3月ごろに国土交通省が公表する日本全国各地に点在する約2万6千ヵ所の標準地と呼ばれる地点の1㎡あたりの適正価格です。
基準地価とは、毎年10月ごろに各都道府県が公表する日本全国各地に点在する約3万ヵ所の基準地と呼ばれる地点の1㎡あたりの適正価格です。
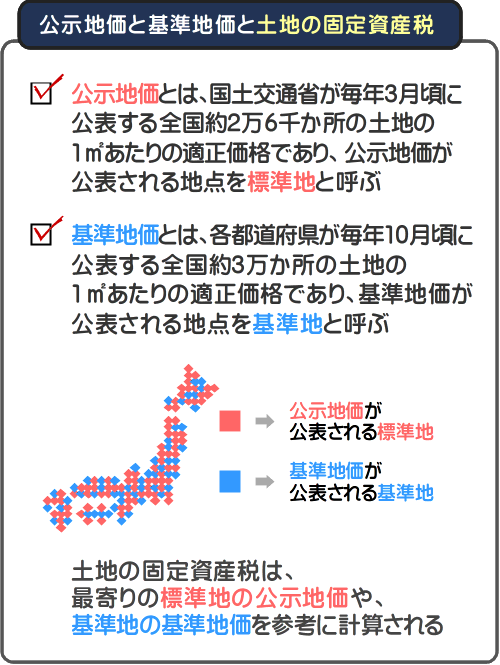
公示地価や基準地価は、付近の土地が売買される際の価格などを参考に設定されます。
そのため、高値で土地が売買される地域に位置する標準地の公示地価や、基準地の基準地価は高くなります。
高値で土地が売買される地域とは、主に立地条件が良い場所です。
よって、公示地価や基準地価を参考に計算される土地の固定資産税は、立地条件が良い場所ほど高くなります。
たとえば、駅や繁華街に近い場所に位置する土地であれば固定資産税は5万円から6万円程度など、立地条件が芳しくない場所に位置する土地であれば固定資産税は2万円から3万円程度などになるという具合です。
家屋の固定資産税はいくらくらいになるか断言できませんが、土地の固定資産税も同じであり、いくらくらいか断言することはできず、立地条件が良ければ5万円から6万円程度など、立地条件が芳しくなければ2万円から3万円程度などとなります。
なお、固定資産税には、住宅が建つ土地に掛かる固定資産税が減額される特例があります。
この特例を住宅用地の特例と呼び(正しくは「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」と呼びます)、家屋と土地がセットになった建売などを購入すれば同特例が適用され、土地部分に掛かる固定資産税が6分の1などに減額されます。
また、更地を購入しつつ注文住宅を建てた場合は、注文住宅が完成した日が属する年の翌年の固定資産税から住宅用地の特例が適用され、土地部分に掛かる固定資産税が6分の1などに減額されます。
先に、「新築の家屋が建つ土地の固定資産税は高ければ5万円から6万円程度、安ければ2万円から3万円程度など」とご紹介しましたが、これらは住宅用地の特例が適用された場合の税額であるため留意してください。
余談ですが、私が運営するもう一つのサイト「固定資産税をパパッと解説」では、住宅用地の特例をわかりやすく解説するコンテンツを公開中です。
新築の家屋が建つ土地に掛かる固定資産税がいくらくらいかお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
関連コンテンツ
住宅用地の特例とは?
2. 一戸建て中古住宅の固定資産税はいくらくらい?
一戸建ての中古住宅を購入すると、一部例外を除き、その家屋と家屋が建つ土地を取得し、その両方に個別に固定資産税が課せられます。
家屋と土地の固定資産税を合計すると、高ければ15万円以上など、安ければ7万円から8万円程度などですが、その家屋の再建築費と築年数、立地条件によって税額が大きく異なります。
以下に、一戸建て中古住宅の家屋と、その家屋が建つ土地に掛かる固定資産税がいくらくらいか簡単にご紹介しましょう
2-1. 一戸建て中古住宅の家屋の固定資産税はいくらくらい?
一戸建て中古住宅の家屋に掛かる固定資産税は、高ければ10万円以上など、安ければ5万円から6万円程度などです。
具体的には、再建築費が高額であり築年数が浅い家屋は固定資産税が10万円以上などと高くなり、再建築費が安く築年数が古い家屋は固定資産税が5万円から6万円程度などと安くなります。
再建築費とは、その家屋と同一の家屋を現時点で新築する際に必要となる材料費と労務費などの合計です。
たとえば、その家屋と同一の家屋を現時点で新築するために、750万円の材料費と750万円の労務費が必要となる家屋があったとしましょう。
その家屋の再建築費は、1,500万円などとなります。
そして、一戸建て中古住宅の家屋に掛かる固定資産税は、その家屋の再建築費から築年数が経過することにより目減りした価値を差し引いた額を基に計算されます。
築年数が経過することにより目減りした価値は、築年数が経過するほど大きくなります。
よって、再建築費が高額であり築年数が浅い家屋は、固定資産税が10万円以上などと高くなりがちです。
反対に、再建築費が安く築年数が古い家屋は、固定資産税が5万円から6万円程度などと安くなります。
再建築費が高額であり築年数が浅い家屋は売買価格も高くなりがちであり、再建築費が安く築年数が古い家屋は売買価格も安くなりがちです。
つまり、一戸建て中古住宅の家屋は、売買価格が高ければ固定資産税も10万円以上などと高くなりがちであり、売買価格が安ければ固定資産税も5万円から6万円程度などと安くなるというわけです。
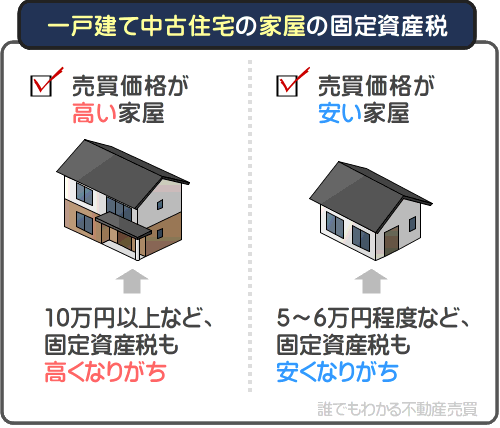
なお、木造家屋の固定資産税は、15年から35年を掛けて新築時の20%まで徐々に下がります。
15年から35年というと開きがありますが、その家屋の延べ床面積1㎡あたりの再建築費が55,120円未満などであれば15年を掛けて、1㎡あたりの再建築費が133,120円以上などであれば35年を掛けて下がることとなります。
つまり、再建築費が高く、なおかつ延べ床面積が狭い木造家屋は固定資産税が下がりにくいというわけです。
ただし、鉄骨鉄筋コンクリート造などの非木造家屋は、1㎡あたりの再建築費を問わず必ず60年を掛けて新築時の20%まで固定資産税が徐々に下がるため留意してください。
一戸建ての家屋といえば主に木造ですが、木造以外であれば固定資産税が下がるのに年数が掛かります。
ちなみに、鉄骨鉄筋コンクリート造などの非木造の家屋といえば、主にマンションです。
マンションは一戸建てより固定資産税が高くて下がりにくといわれますが、このことなどが理由です。
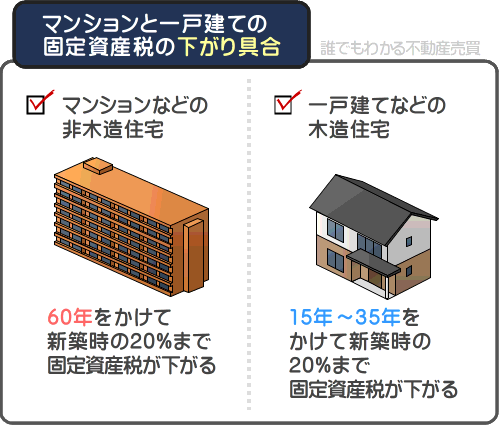
2-2. 一戸建て中古住宅の土地部分の固定資産税はいくらくらい?
一戸建て中古住宅の家屋が建つ土地に掛かる固定資産税は、高ければ5万円から6万円程度など、安ければ2万円から3万円程度などです。
一戸建て中古住宅の家屋が建つ土地に掛かる固定資産税は、この記事の「1-2. 新築の一戸建ての土地部分の固定資産税はいくら?」にてご紹介した新築の家屋が建つ土地に掛かる固定資産税と同じ方法で計算されます。
また、一戸建て中古住宅の家屋が建つ土地にも、新築の家屋が建つ土地と同じく住宅用地の特例が適用されます。
よって、一戸建て中古住宅の家屋が建つ土地に掛かる固定資産税は、新築の家屋が建つ土地に掛かる固定資産税と同じく、高ければ5万円から6万円程度など、安ければ2万円から3万円程度などとなります。
なお、この記事の「2-1. 一戸建て中古住宅の家屋の固定資産税はいくらくらい?」にて、家屋に掛かる固定資産税は築年数が経過することにより下がるとご紹介しましたが、土地に掛かる固定資産税は、その土地に建つ家屋の築年数が経過しても下がることはありません。
家屋が建つ土地に掛かる固定資産税は、その周辺の地価に応じて変動します。
たとえば、駅ができるなどしてその周辺の地価が上昇すれば、その土地の固定資産税も上がるといった具合です。
反対に、周辺の地価が下落すれば、その土地の固定資産税も下がることとなります。
ただし、土地に掛かる固定資産税は、急激に上昇することはないためご安心ください。
理由は、納税者の負担を軽減するために、土地に掛かる固定資産税には負担調整措置が設けられているためです。
固定資産税の負担調整措置とは、土地の所有者の税負担が急激に大きくなることを防ぐための措置であり、負担調整措置があることにより、土地の固定資産税が上がる際は徐々に上がることとなります。
固定資産税の負担調整措置は、私が運営するもう一つのサイト「固定資産税をパパッと解説」にてわかりやすくご説明しています。
一戸建て中古住宅の購入をご予定の方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
関連コンテンツ
固定資産税の負担調整措置とは?
まとめ - 借地権であれば土地部分の固定資産税は掛からないが…
はじめて不動産を購入する方へ向けて、新築の一戸建てと、一戸建て中古住宅の固定資産税がいくらくらいかご紹介しました。
新築の一戸建ての固定資産税は、家屋と土地と合わせて高ければ25万円以上など、安ければ12万円から13万円程度などです。
一戸建て中古住宅の固定資産税は、家屋と土地と合わせて高ければ15万円以上など、安ければ7万円から8万円程度などとなります。
不動産の固定資産税は物件によって異なるため、いくらくらいと断言できませんが、おおむねこの程度とお考えください。
購入を希望する不動産の固定資産税は、その不動産を取り扱う不動産業者に問い合わせることにより大まかな税額を確認することが可能です。
なお、この記事の本文中にて、「一戸建てを取得すると、一部例外を除き家屋と土地の両方を取得し、その両方に固定資産税が課せられる」とご紹介しました。
ここで気になるのが、上記の文章に含まれる「一部例外」ですが、主に借地権を指します。
不動産検索サイトで不動産を検索すると相場より大幅に安い一戸建てや土地がヒットし、詳細を確認すると「借地権」と記されていることがあります。
借地権とは、土地を借り、借りた土地に家を建てるなどして利用できる権利です。
借地権の物件の土地部分は、購入するのではなく借りることとなります。
そして、借地権で借りた土地部分の固定資産税は、地主が負担します。
一部例外とは借地権であり、借地権の土地は購入したこととならず、土地の借り主が固定資産税を負担する必要はありません。
よって、固定資産税を節約したいのであれば借地権がお勧めであるといいたいところですが、借地権で借りた土地は定期的に地代を支払う必要があると共に、その土地に建つ家屋を売却する際は地主の承諾を得る必要があるため注意してください。
ご紹介した内容が、不動産の固定資産税がいくらくらいかお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
最終更新日:2021年9月
記事公開日:2018年8月
こちらの記事もオススメです
