買って大丈夫?長期優良住宅のデメリットをイラスト付きで解説
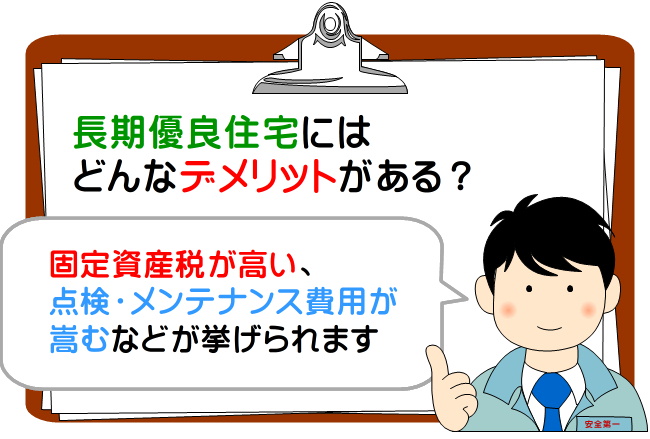
長期優良住宅とは、市区町村などから優秀であると認定された住宅であり、取得すれば住宅ローン減税でより多くの所得税が減税されるなどのメリットがあります。
しかし、定期的なメンテナンスが必要などのデメリットがあり、長期優良住宅を購入したものの後悔している方や、認定を取り消したいと希望する方が少なからずいらっしゃるようです。
そこで、今回の誰でもわかる不動産売買では、長期優良住宅の購入を希望する方へ向けて、デメリットをわかりやすく解説しましょう。
目次
- 1. 定期的な点検と記録が必要
- 2. メンテナンスが必要
- 3. 固定資産税が高い
- まとめ - それでも長期優良住宅は増えている
1. 定期的な点検と記録が必要
長期優良住宅は75~90年以上の耐久性があるように設計されていますが、定期的なメンテナンスを実施しなくてはその性能を発揮できません。
よって、長期優良住宅の所有者は、少なくとも取得後30年間にわたり10年に1度の間隔で点検を実施する必要があります。
点検には費用が掛かり、その費用は長期優良住宅の所有者が負担することとなります。
この費用を負担することが、長期優良住宅を購入することのデメリットのひとつです。
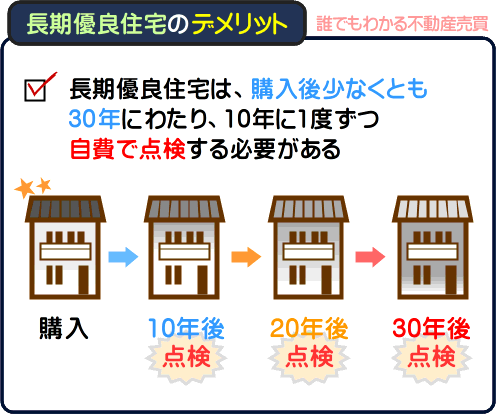
点検すべき箇所は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の第二条の3号にて規定され、同号の内容は以下のとおりとなっています。
- 住宅の構造耐力上主要な部分
- 住宅の雨水の浸入を防止する部分
- 住宅の給水又は排水の設備
上記の内容は抽象的であり、点検すべき具体的な箇所が把握できませんが、国土交通省が公開する資料「長期優良住宅認定制度の技術基準の概要について」の18ページには、一戸建て木造住宅における点検箇所と点検すべき周期の例が記され、その内容は以下のとおりです。
国土交通省が公開する資料における具体的な点検箇所の例
| 点検箇所 | 点検すべき周期 |
|---|---|
| 柱や筋交いなど壁を構成する建材の傾きや腐朽など | 10年に1度 |
| 棟木や野地板など屋根を構成する建材からの雨漏り | 〃 |
| 瓦やアスファルトシングルなど屋根材の剥がれやずれ | 5年に1度 |
| 基礎のひび割れや基礎部分に設置された換気口のふさがり | 〃 |
| 大引きや根太、土台など床下の建材の腐朽やシロアリによる食害 | 〃 |
| 給排水管からの漏水 | 〃 |
| サイディングなど外壁材の欠損 | 3年に1度 |
| 雨樋の破損や詰まり | 〃 |
| 軒裏の建材の腐朽や剥がれ | 〃 |
また、震度6以上の地震が発生した後や、その長期優良住宅が所在する地域に台風による特別警報が発令された後なども臨時点検が必要となります。
10年に1度の点検や臨時点検は、その長期優良住宅を販売、または建築した業者に依頼するのが通例ですが、他の業者に依頼することも可能であり、点検費用は依頼先によって異なるものの概ね5~6万円などです。
そして、点検完了後は自らが点検結果を記録しつつ保管する必要があり、その手間も長期優良住宅を所有することのデメリットのひとつといえます。
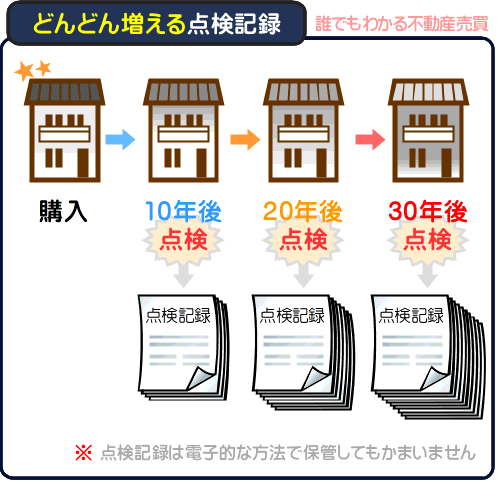
なお、長期優良住宅を所有すると、その住宅を長期優良住宅に認定した市区町村などから点検記録の提出などを求められることがあります。
要請に応じない場合や、虚偽の記録を提出した場合などは30万円以下の罰金刑に処せられる場合があるため注意してください。
国土交通省が公布する「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」の裏面には、その詳細が掲載されています。
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ
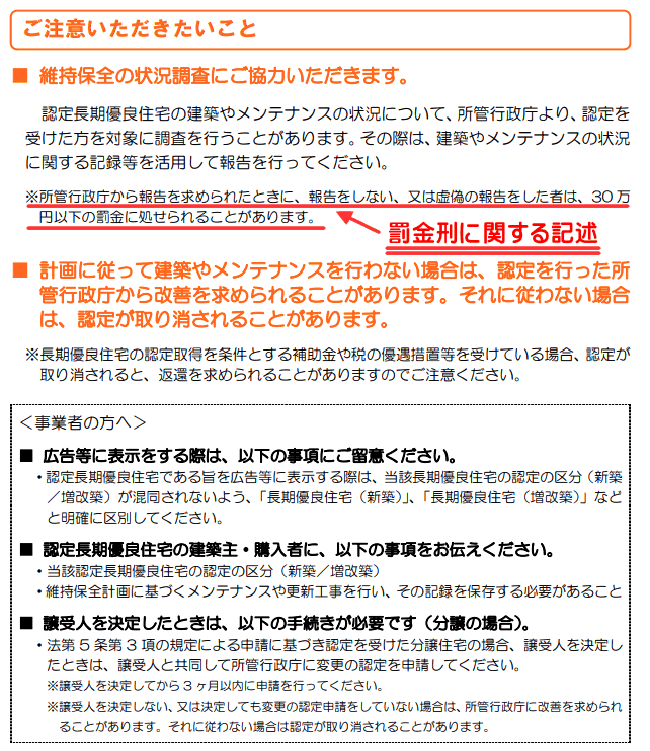
出典:国土交通省「長期優良住宅のページ」
2. メンテナンスが必要
長期優良住宅を所有すると、30年間にわたり10年に1度など自費で点検を実施する必要がありますが、点検結果が芳しくない場合はメンテナンスをしなくてはなりません。
メンテナンスに掛かる費用は点検費用と同じく自らが負担する必要があり、このようなランニングコストが掛かることが長期優良住宅のデメリットのひとつです。
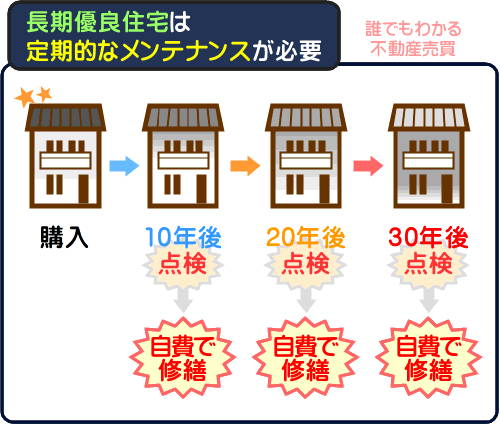
そして、メンテナンスが必要な状態であるにもかかわらず実施しない場合は、その住宅を長期優良住宅に認定した市区町村などから改善を求められる場合があります。
改善に応じない場合は、長期優良住宅の認定を取り消されることがあるため注意が必要です。
長期優良住宅を所有すると、住宅ローン減税でより多くの所得税が減税される、フラット35の金利が引き下げられるなどの金銭的なメリットがありますが、認定が取り消されればそれらの特典は取り消されます。
取り消されるだけであればさほど問題はありませんが、場合よってはそれまでの減税分や、引き下げられていたフラット35の金利分を請求されることがあるため気を付けなくてはなりません。
このように認定が取り消された場合に減税分などを支払わなければならないことや、メンテナンス費用が掛かることなどが長期優良住宅のデメリットです。
3. 固定資産税が高い
長期優良住宅の最も大きなデメリットといえば、高い固定資産税です。
固定資産税とは、不動産の所有者に毎年課せられる税金であり、住宅の建物部分の固定資産税は、その建物の価額(価値から鑑みた価格)に応じて課税されます。
たとえば、建築費が安い住宅は価額が低いと見なされ固定資産税が安くなり、建築費が高い住宅は価額が高いと見なされ固定資産税が高額になるという具合です。
長期優良住宅は、一般的な住宅より耐久性を重視しつつ設計されているため建築費が高額であり、価額が高いと見なされます。
そのため、長期優良住宅は一般的な住宅より固定資産税が高くなるのが通例であり、その高い税額がデメリットとなります。
どの程度高くなるかは、その長期優良住宅によって異なるため断言できませんが、建物部分の建築費が3,000万円の長期優良住宅であれば、固定資産税はその1.4%の42万円などです。( ※ 販売価格ではなく建築費が3,000万円の場合の税額であるため注意してください。建築費は販売価格の5~6割程度などです )
さらに、市街地に位置する長期優良住宅には都市計画税も課せられます。
建物部分の建築費が3,000万円の長期優良住宅の都市計画税は、その0.3%の9万円です。
このように長期優良住宅は、固定資産税や都市計画税が高くなるのがデメリットです。
なお、先に建築費が3,000万円の長期優良住宅を購入すると42万円の固定資産税が課せられるとご紹介しましたが、固定資産税は建物部分と土地部分の両方に課せられます。
よって、長期優良住宅を購入すると、42万円などの建物部分の固定資産税に加え、土地部分に対する固定資産税も課せられるため留意してください。
ただし、新築された一戸建ての長期優良住宅を購入すると取得後5年間など、新築されたマンションの長期優良住宅を購入すると取得後7年間などにわたり、建物部分の固定資産税が2分の1に軽減されます。
まとめ - それでも長期優良住宅は増えている
長期優良住宅のデメリットをご紹介しました。
長期優良住宅には、以下のデメリットがあります。
長期優良住宅のデメリット
- 自費で10年に一度などの間隔で点検を行い、必要に応じてメンテナンスを実施する必要がある
- 点検の度に結果を記録しつつ保管し、市区町村などから要請があれば点検記録を提出する必要があり、その住宅が長期優良住宅としての品質を満たさないと判断された場合は改善命令を受けることがある
- 固定資産税が高い
以上が長期優良住宅のデメリットであり、購入したものの後悔している方や、やめた、いらないとお嘆きになる方が少なからずいらっしゃるようです。
長期優良住宅の購入をご検討の方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。
なお、国土交通省が公開する資料「長期優良住宅制度のあり方に関する検討会最終とりまとめ」によれば、長期優良住宅は近年では毎年10万戸ずつ増え、令和2年の時点で約100万戸が存在するとのことです。
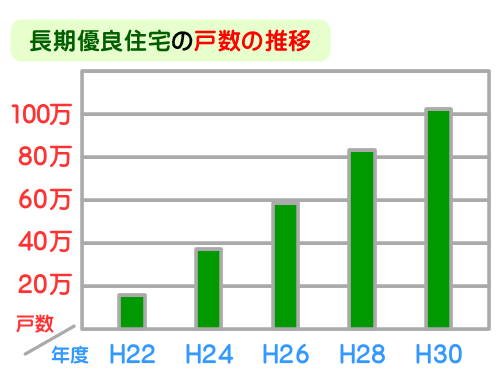
つまり、長期優良住宅にはデメリットがあるものの、75年以上の耐久性を有する構造は、消費者のニーズに合致すると考えられるというわけです。
また、長期優良住宅は10年に一度などの間隔で定期的に点検とメンテナンスを実施する必要がありますが、それは一般的な住宅も同じです。
よって、孫子の代まで長く居住できる住宅の購入を希望される方は、前向きに長期優良住宅の購入をご検討されるのが良いでしょう。
ちなみに、誰でもわかる不動産売買では、長期優良住宅の詳細やメリットをわかりやすく解説するコンテンツも公開中です。
お時間のある方は、ぜひご覧ください。
関連コンテンツ
長期優良住宅とは?わかりやすく解説(簡単・簡潔・よくわかる)
ご紹介した内容が、長期優良住宅をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
記事公開日:2020年12月
こちらの記事もオススメです
