取引事例比較法とは?わかりやすく解説
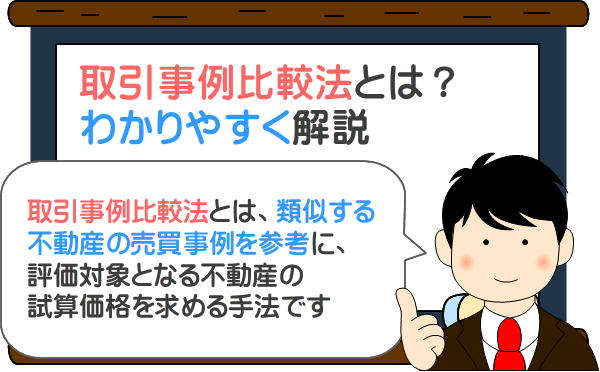
取引事例比較法とは、類似する不動産の売買価格を参考に、評価対象となる不動産の試算価格を求める手法です。
取引事例比較法をわかりやすく解説し、取引事例比較法を用いて不動産の価格を求める流れを簡単にご紹介しましょう。
目次
1. 取引事例比較法とは、類似する売買事例を参考に不動産の価格を求める手法
それでは、取引事例比較法をわかりやすく簡単に解説します。
その前に、不動産鑑定士という資格を理解してください。
不動産鑑定士の資格とは、不動産を鑑定しつつ適正な価格を評価し、評価結果をまとめた鑑定評価書を作成できる国家資格であり、同資格を有しつつ不動産を鑑定する職業に就く者を不動産鑑定士と呼びます。
不動産鑑定士が評価した不動産の適正な価格は、不動産が売買される際の価格の指標や、土地を所有することにより課せられる固定資産税の額を計算する基などとして活用されます。
その不動産鑑定士が、不動産の試算価格を求める際に用いる手法のひとつが取引事例比較法です。
取引事例比較法とは、状況などが類似する不動産が売買された事例を参考に、不動産鑑定士が評価対象となる不動産の試算価格を求める手法を意味します。
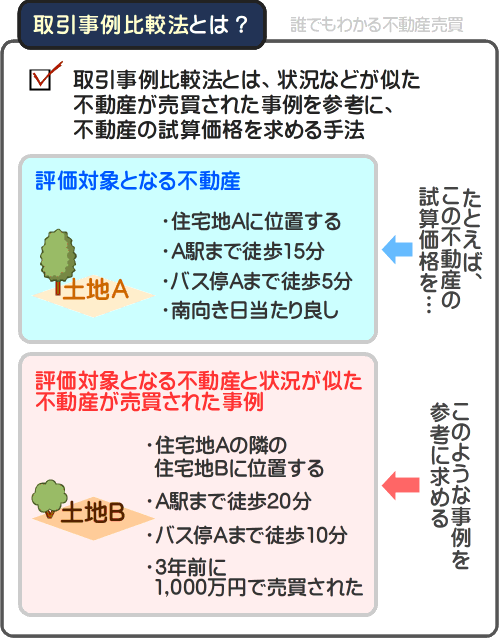
不動産鑑定士が取引事例比較法を用いて不動産の試算価格を求める際は、第一に評価対象となる不動産の周辺などで行われた、評価対象となる不動産と類似する不動産が売買された事例を収集します。
第二に、収集した中に特殊な事情を含みつつ売買価格が決定した事例があれば、特殊な事情を含まず売買されたと見なしつつ価格を補正します。
特殊な事情とは、売り主と買い主の知識不足や、不動産の供給不足などにより相場と掛け離れた価格で売買されたなどの事情であり、価格を補正することを事情補正と呼びます。
加えて、収集した中に現在とは異なる価格水準で売買価格が決定した事例があれば、現在の価格水準で売買されたと見なしつつ価格を修正します。
現在の価格水準で売買されたと見なしつつ価格を修正することを時点修正と呼びます。
第三に、収集した事例と評価対象となる不動産を比較し、評価対象となる不動産の試算価格を求めます。
求められた試算価格が取引事例比較法により求めた不動産の試算価格であり、取引事例比較法を用いて求めた不動産の価格を比準価格と呼びます。
ポイント
取引事例比較法を用いて求めた不動産の試算価格を比準価格と呼ぶ
不動産鑑定士が取引事例比較法を用いて不動産の試算価格を求める流れを図解でわかりやすく簡単に解説すると以下のとおりです。
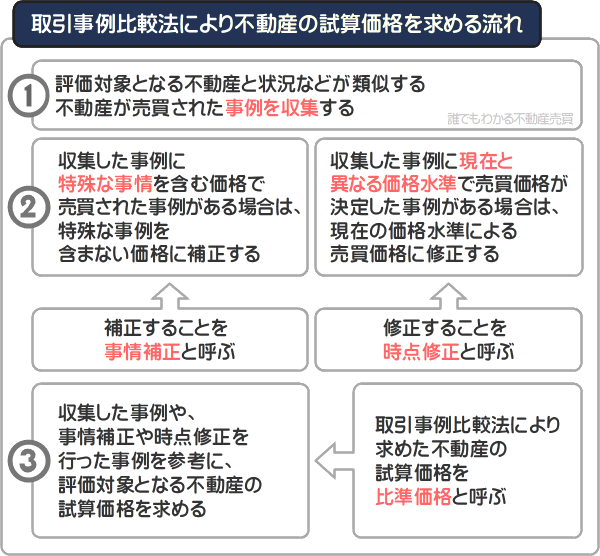
なお、取引事例比較法は、類似する不動産が売買された事例が多く存在する不動産の試算価格を求める場合のみに活用できるため留意してください。
取引事例比較法とは、類似する不動産が売買された事例を参考に、評価対象となる不動産の試算価格を求める手法です。
よって、類似する不動産が売買された事例がない、または事例が少ない場合は、取引事例比較法を用いて不動産の試算価格を求めることはできません。
取引事例比較法の詳細は、国土交通省が定めた不動産鑑定士が不動産の適正な価格を求める際の基準「不動産鑑定評価基準」の「総論 第7章 鑑定評価の方式 第1節 価格を求める鑑定評価の手法 Ⅲ 取引事例比較法」に記されています。
取引事例比較法の詳細をご確認されたい方がいらっしゃいましたら、ぜひ不動産鑑定評価基準をご覧ください。
つづいて、不動産鑑定士が取引事例比較法を用いて不動産の試算価格を求める流れをもう少し詳しくわかりやすくご説明しましょう。
2. 取引事例比較法で不動産の試算価格を求める流れ
取引事例比較法とは、類似する不動産の売買価格を参考に、評価対象となる不動産の試算価格を求める手法であり、不動産鑑定士が不動産の適正な価格を評価する際に活用します。
ここから、不動産鑑定士が取引事例比較法を用いて評価対象となる不動産の試算価格を求める流れをわかりやすく簡単にご紹介しましょう。
2-1. 近隣地域などで行われた不動産売買の事例の収集と選択
まずは、評価対象となる不動産の近隣の地域などにおいて行われた、評価対象の不動産と類似する不動産が売買された事例を収集します。
そして、収集した中から、以下の3つの要件を全て満たす事例のみを選択します。
- 買い主や売り主の知識不足により相場と異なる価格で売買された、売買価格に不動産の価格以外の代金が含まれていたなどの「特殊な事情」を含まない価格で売買された事例、または、特殊な事情を含みつつ売買されたものの、特殊な事情を含まず売買されたと見なしつつ売買価格を補正できる事例
- 現在と異なる価格水準で行われた売買である場合は、現在の価格水準で売買が行われたと見なしつつ売買価格を修正できる事例
- 評価対象となる不動産と立地条件や構造が似ているなど、評価対象の不動産と比較できる不動産が売買された事例
2-2. 事情補正と時点修正
事例の収集が完了し、収集した事例に特殊な事情を含む価格で売買された事例がある場合は、その売買価格を補正します。
具体的には、「特殊な事情を含みつつ売買された価格」を「特殊な事情を含まない価格で売買された」と見なしつつ売買価格を補正し、補正することを事情補正と呼びます。
加えて、収集しつつ選択した事例に現在と異なる価格水準で売買された事例が含まれる場合は、その売買価格を修正します。
具体的には、「現在と異なる価格水準で売買された価格」を「現在の価格水準で売買された価格」と見なしつつ修正し、修正することを時点修正と呼びます。
事情補正と時点修正の詳細は、不動産鑑定評価基準の「総論 第7章 鑑定評価の方式 第1節 価格を求める鑑定評価の手法 Ⅲ 取引事例比較法」の「2,適用方法(2)事情補正及び時点修正」にて確認することが可能です。
2-3. 事例を参考に評価対象となる不動産の試算価格を求める
事情補正と時点修正が完了すれば、評価対象となる不動産と収集した事例を比較し、収集した事例の売買価格を参考に評価対象となる不動産の試算価格を求めます。
比較する項目は、地域要因と個別的要因に分けられ、地域要因とはその地域の状況であり、個別的要因とは個々の不動産の現状です。
比較すべき地域要因と個別的要因をわかりやすく簡単にご紹介すると以下のようになります。
- 地域要因
- 地域要因とは不動産が所在する地域の状況であり、地域の日照状況、道路の通りやすさ、都心への距離、商業施設の有無、上下水道やガスの供給状況、インターネット回線の配備状況、公害の有無などを指します。
- 個別的要因
- 個別的要因とは個々の不動産の建物や土地の現状であり、築年数や構造、延べ床面積、施工の質、耐震性や耐火性、維持管理状態、建材に含まれる人体に有害な物質の有無、駐車場や庭の有無、商業施設への距離、上下水道の引き込み状況、インターネット回線の引き込みのしやすさなどです。
地域要因と個別的要因を比較しつつ求めた評価対象となる不動産の試算価格が取引事例比較法により求めた不動産の価格です。
取引事例比較法により求めた不動産の試算価格を比準価格と呼びます。
なお、比較すべき地域要因の詳細は、不動産鑑定評価基準の「総論 第3章 不動産の価格を形成する要因」の「第2節 地域要因」にて確認することが可能です。
また、比較すべき個別的要因の詳細は、同じく不動産鑑定評価基準の「総論 第3章 不動産の価格を形成する要因」の「第3節 個別的要因」にてご確認いただけます。
まとめ - 取引事例比較法以外にも原価法と収益還元法がある
取引事例比較法をわかりやすく簡単に解説しました。
取引事例比較法とは、不動産鑑定士が不動産の試算価格を求める手法のひとつであり、類似する不動産が売買された際の価格を参考に、評価対象となる不動産の試算価格を求める手法です。
難しいと感じる方は、取引事例比較法とは、似たような不動産の売買価格を参考に、不動産の適正価格を求める方法などとお考えになれば簡単です。
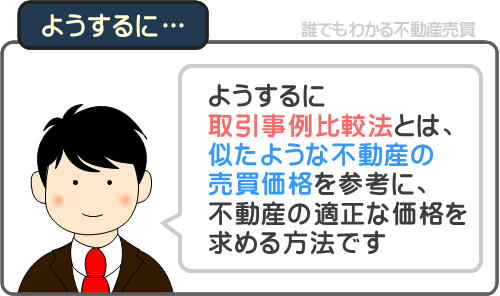
ただし、取引事例比較法は、似たような不動産が売買された事例がなければ活用できないため留意してください。
取引事例比較法は似たような不動産が売買された事例が多い場合に有効であり、似たような不動産が売買された事例が少なければ活用できません。
取引事例比較法は、数多くの事例を収集し、慎重に吟味しつつ比較することにより評価の精度が高まります。
取引事例比較法の詳細は、国土交通省が定めた不動産鑑定士が不動産の適正な価格を評価する際の基準「不動産鑑定評価基準」にて確認することが可能です。
取引事例比較法をお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。
なお、不動産鑑定士が不動産の試算価格を求める際は、今回ご紹介した取引事例比較法に加え、原価法と収益還元法という方法も活用します。
原価法とは、評価対象となる不動産と同等の不動産を入手するために必要となる費用を調査し、調査結果から不動産の試算価格を求める手法です。
収益還元法とは、評価対象となる不動産を所有することにより得る収益から、評価対象となる不動産の資産価格を求める手法を意味します。
誰でもわかる不動産売買では、原価法と収益還元法をわかりやすく解説するコンテンツも公開中です。
不動産鑑定士が不動産を鑑定する際の手法にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
関連コンテンツ
・原価法とは?わかりやすく解説
・収益還元法とは?わかりやすく解説
ご紹介した内容が、取引事例比較法をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
最終更新日:2022年1月
記事公開日:2019年12月
こちらの記事もオススメです
